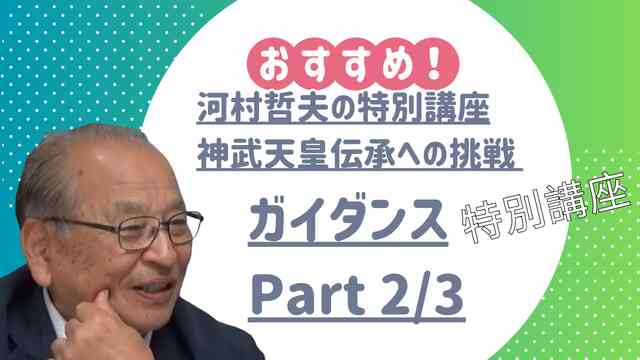目次
戦後史観・統計的年代論・「日本のルーツ」再点検
戦後の日本では、『古事記』『日本書紀』を学校教育の中心で体系的に学ぶ機会が、意外なほど少なくなっていきました。歴史の授業では触れられても、本文を読み込み、成立事情や史料批判まで踏み込むことは稀だったように思います。その結果として「古代のことは語りにくい」「神話や天皇伝承は学術の外側に置くものだ」という空気が強まり、古代天皇の実在性や伝承の意味をめぐる議論そのものが、次第に避けられてきた面があります。

とりわけ神武天皇や神功皇后のような人物は、戦前には大きく語られ、戦後には逆に「語ること自体が時代錯誤」と見なされがちになりました。学界でも否定的な見解が強く、神武天皇について言及すると「戦前の亡霊」といった扱いを受ける。そうした風潮が、少なくともこの70年ほど続いてきたと言えるでしょう。
しかし、ここで一度立ち止まって考えたいのです。『日本書紀』の年代が不自然だからといって、その内容全体が虚構だと即断できるのか。年代が誤っている可能性と、伝承そのものの歴史的核の有無は、分けて考えるべきではないのか。そうした問題提起を、統計学・データ分析の観点から真正面に行った研究者として、安本美典先生の名が挙がります。
日本書紀に記載されている年代の補正方法
安本先生は40年以上前に「統計的年代論」を提示し、『日本書紀』の年代表記には決定的な歪みがある一方で、そこに含まれる出来事の配列や伝承の骨格そのものは、適切な補正を施せば史実に近づきうる、という立場を示しました。つまり「年代がズレている=全否定」ではなく、「年代を補正すれば読める」という方向へ議論を転換したのです。
その結果として提起されたのが、卑弥呼と神功皇后、さらには神武天皇を含む「古代王権像」の再配置です。安本先生の枠組みでは、邪馬台国は九州(とりわけ甘木・朝倉周辺)に比重を置いて捉えられ、九州勢力が近畿へ移動・統合していくという大きな流れが、古代文献の“統一見解”として浮かび上がる、とされます。ここで重要なのは、九州説/近畿説の対立を煽ることではなく、文献の年代配置を補正したときに、史料相互の符合が増えるかどうか、という検証の姿勢です。
神武天皇の年代
具体例として、神武天皇の寿命・在位年数は『日本書紀』のままでは極端です。初代神武天皇が127歳で没し、しかも即位から非常に長期にわたり統治した、という形になっている。これが現実的でないことは直感的にも明らかで、「暦が引き伸ばされている」「倍暦のような処理があるのでは」といった仮説が出るのも自然です。
安本先生の統計的年代論では、神武天皇は紀元前660年ではなく、もっと後の時期、大まかにみて西暦3世紀末〜4世紀前半あたりの人物像として再配置されます。そうすると、縄文時代に即位したかのような矛盾は薄まり、古墳時代の開始や、東アジア史の動きとも整合しやすくなる、という感覚が出てきます。
神功皇后の年代

さらに象徴的なのが神功皇后です。『日本書紀』では神功皇后が100歳で没し、仲哀天皇崩御後に摂政として長期間政治を担い、年代は201年〜269年付近に置かれる形になります。ここが何を意味するかというと、卑弥呼の時代と年代が重なるのです。そのため戦後史観の一部では「神功皇后=卑弥呼の反映(あるいは混入)」のように理解され、『日本書紀』の神功紀が史実ではなく作為である、という議論が強まりました。
ところが安本先生の補正では、神功皇后の活躍年代は概ね390年〜410年頃へと移動します。ここで話が面白くなるのは、朝鮮半島側の同時代資料との符合が生まれる点です。たとえば高句麗の広開土王碑には、391年頃をめぐる倭勢力の動きが刻まれているとされます(解釈には諸説ありますが、「倭が半島に関与した」こと自体を示す資料として注目されてきました)。もし神功皇后伝承が「朝鮮出兵・対外遠征」という核を持つなら、その核が4世紀末の東アジア情勢と結びつく形で理解できる可能性が出てきます。北部九州に神功皇后に関する伝承地が非常に多い、という点も、単なる作り話として片付けにくい“分布”の問題として浮上してきます。
倭の五王の年代

そして応神天皇、仁徳天皇、雄略天皇の時代へと進むにつれ、中国側史料に「倭の五王」が現れ、国内では稲荷山鉄剣銘(ワカタケル大王など)といった金石文資料が関わってくる。こうした外部史料・考古資料と、補正された年代帯が重なっていくほど、「日本書紀の年代はそのままでは無理があるが、補正すると史料群が噛み合い始める」という方向性が、少なくとも仮説として説得力を持ちます。要するに、否定か肯定かの二択ではなく、補正して検証できるという地平が開けるのです。
また『日本書紀』は、成立(720年)後すぐに宮中行事としての「日本書紀講筵(こうえん)」が行われ、国家的な学習・講義の場が制度化されたことも重要です。翌年から数十年ごとに大規模な講筵が開かれ、貴族や官人が参加し、テキスト(訓点資料のようなもの)も整えられていった。つまり『日本書紀』は単なる“本”ではなく、国家が自らを語るための公式テキストとして運用され、読み継がれた。
その蓄積があるからこそ、私たちは今日、訓点や注釈を手掛かりにして本文を読めるわけです。一方で、この講筵がやがて途絶え、戦乱期に入るにつれ、優雅な学術行事が失われていく流れも見えてきます。そう考えると、いま改めて『日本書紀』を読み直す営みは、ある意味で「現代における講筵」と言ってもよいのかもしれません。
神武東征の歴史上の位置づけ
ここで神武天皇の問題に戻ります。現代日本では2月11日が建国記念の日とされ、神武天皇の即位(紀元前660年)を起点とする国家像が、象徴的に置かれてきました。しかし邪馬台国(卑弥呼)の時代を2〜3世紀と見るなら、『日本書紀』の年代をそのまま採用した瞬間に、東遷説(九州から近畿へ)が成立する余地が狭まります。神武が紀元前なら、卑弥呼ははるか後代であり、九州勢力の移動と統合というストーリーが切断されてしまう。ところが統計的年代論で神武の年代を後ろへ動かすと、卑弥呼の後に神武が登場しうる構図が見えてくる。すると「邪馬台国→九州勢力→近畿へ」という長い連鎖が、文献上でも再構成可能になるわけです。
この「九州勢力の東遷・統合」という発想は、実は戦前戦後を通じて、複数の重鎮研究者たちが自然に触れてきたテーマでもあります。表現や評価はさまざまでも、「ヤマタイ(邪馬台国)とヤマト(大和)の関係をどう繋ぐか」という問いが、学界の底流にあり続けたことは確かです。安本先生は、年代補正という技術でそこに再び切り込み、「卑弥呼=神功皇后」も含めた統合的理解を提案した。その射程は、単なる人物比定の話にとどまらず、古代国家形成の時間軸そのものを再構築する作業だと言えます。
中国側の歴史認識との対応
さらに視野を広げると、この問題は1000年前の中国側史書にも接続します。宋代に編纂された『新唐書』「日本伝」は、中国が当時得ていた日本情報を整理し直した“対外的な統一見解”とも言える位置づけを持ちます。そこでは日本の起源として「倭(倭国)」「日本」という二重の呼称問題が整理され、冒頭で「漢の倭の奴国王が金印を受けた」という話が置かれます。
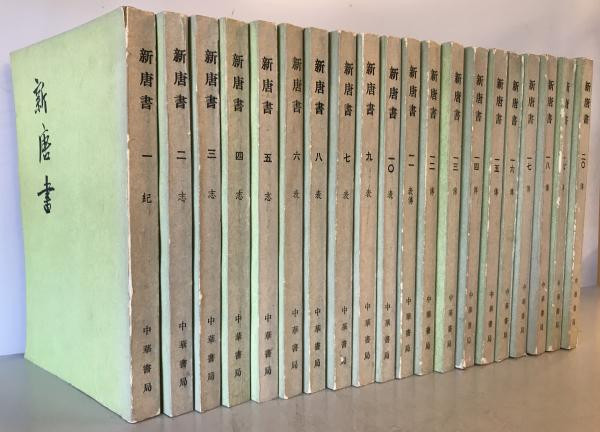
つまり中国側から見た「日本のルーツ」は、まず那(奴)国=北部九州の対外関係から語られる。さらに神々の系譜や、九州を基点とする伝承、そして神武天皇の移動(東遷)に類する理解が記されている、という読み方も可能になります。これが意味するのは、神武天皇伝承が日本国内だけの“後世の創作”として閉じているのではなく、東アジア世界の知識体系の中で、一定の形をもって把握されていた可能性がある、という点です。
懐疑的視点も同時に持つ
もちろん、これらをもって即断はできません。資料は批判的に読むべきであり、広開土王碑の解釈も含め、諸説はあります。しかし、戦後的な「語らない」「最初から否定する」という態度ではなく、年代補正・外部史料・伝承分布・金石文など複数のデータを束ねながら、仮説として組み立て直すことは可能です。そしてそれこそが、この講座が掲げる「神武天皇伝承への挑戦」の具体的な方法論なのだと思います。
次回は、この流れを受けて、神武天皇伝承を九州の地理・ルート・地域伝承の分布と照らし合わせながら、どこまで“歴史の核”を復元できるのか。その作業に踏み込んでいきたいと思います。